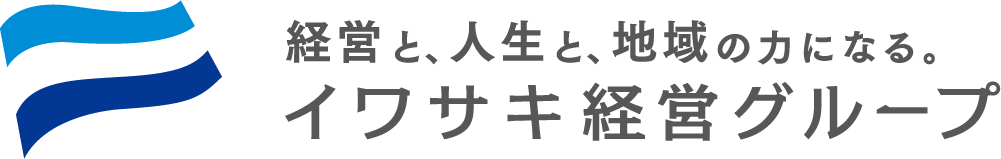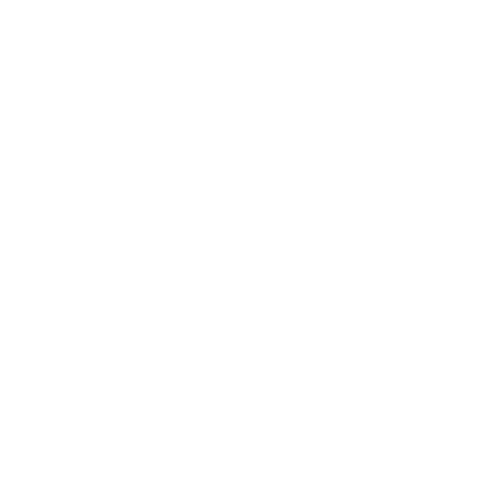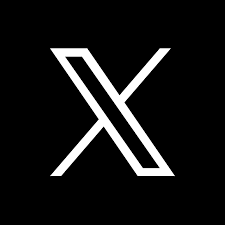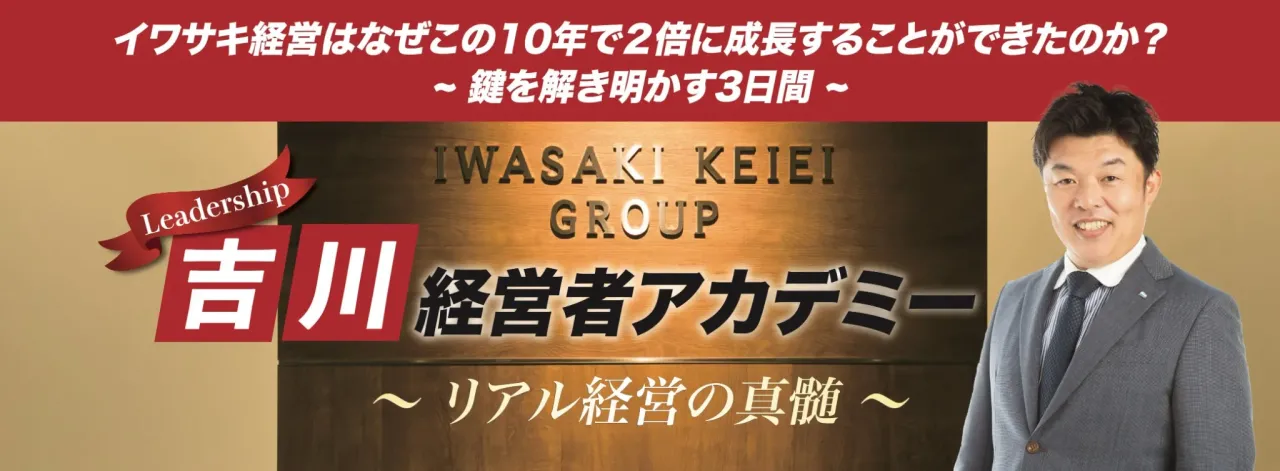イワサキ経営スタッフリレーブログ
2025年07月
2025.07.26
「今行ける能登」
「今行ける能登」というものを御存じでしょうか。
これは能登地域で安全に行ける施設や観光地などをまとめた、石川県観光連盟ウェブサイトで公開されているデジタルマップのことです。通行可能な道路状況やバスの運行もどこまでされているかも確認でき、観光地・飲食店などカテゴリー別の検索機能もある利便性が高く使いやすいところが魅力です。「観光地」をクリックしてみると体験・寺社仏閣などさらに細かく分類され、施設の詳細や営業時間・駐車場の案内等も確認することができ、さらにマップ上でみることができるので視覚的にも観光ルートを選定することに役立つことがわかります。
2024年1月1日の地震と2024年9月21日からの大雨により被害を受けた能登半島。土地の隆起や土砂災害等の複合災害の状況になっており、支援の遅れ等が問題になっていました。現在は交通空白も改善され、営業を再開している観光地や宿泊施設も多々ありますが「どこまで行けるのか」「どれくらい時間がかかるのか」など観光することへの不安が多くあることも理解できますし、地域の被害の状況によって震災前とは営業状況が異なる場合もあります。その不安を解消するためのデジタルマップです。
石川県では、2024年の観光入り込み客数は前期比12.4%減の約1886万人、地域別にみると能登地域が前期比54%減の約284万人となっており大きく被災の影響が出ていることがわかります。特に能登地域は観光資源に恵まれており和倉温泉や輪島朝市などが多くの観光客を集めており、観光業が主要産業の一つにもなっており地域経済を支えています。その地域経済をささえる観光業の復興をどのように進めるかが課題になっています。2024年では各種旅行サイトによる北陸応援割、いしかわ応援割など能登半島地震被災地域への観光復興支援が見受けられました。今年はどうなるのでしょうか。
「今行ける能登」を活用して是非、能登地域へ観光支援をしてみてはいかがでしょうか。
イワサキ経営グループ 監査部三課 福地晏
2025.07.08
気温と売上の相関について
気温は私たちの生活に密接に関わっており、日常の消費行動に大きな影響を与える要因の一つです。特に小売業や飲食業、アパレル業界などでは、気温の変化に応じて商品の売れ行きが大きく変動することが多く、企業にとって重要なマーケティング指標となっています。
たとえば、夏の暑い日には冷たい飲料やアイスクリームの売上が急増し、逆に気温が低い日には温かい飲み物や鍋料理の需要が高まるといった現象は、誰もが経験的に理解しているでしょう。同様に、気温が上昇するとTシャツやサンダルといった夏物衣料が売れ、気温が下がるとコートやマフラー、ヒートテックなどの防寒用品の売上が伸びます。こうした動きは一時的な流行ではなく、気温と消費行動の間に明確な相関関係があることを示しています。
近年では、この関係性をより正確に捉えるために、企業は気象データを活用した売上予測の高度化を進めています。たとえば、コンビニエンスストアやスーパーでは、過去の販売実績と天気情報をもとにAIを活用して、明日の気温に応じた商品の仕入れ数を調整しています。これにより、無駄な在庫や品切れを防ぎ、効率的な商品管理が可能となります。また、オンライン広告においても、ユーザーの地域の気温に連動して商品をレコメンドするような工夫がされており、購買意欲を高める施策として注目されています。
さらに、気候変動が進む現代においては、従来の季節パターンが崩れつつあります。以前は「夏は7月から」「冬は12月から」といった感覚がありましたが、今では5月に真夏日が観測されたり、11月でも気温が20度を超えたりする日があるなど、売れ筋商品のタイミングも年々予測が難しくなっています。このような状況下では、リアルタイムの気温情報を柔軟に取り入れた商品戦略やプロモーションが、企業の競争力を左右する鍵となるでしょう。
実際に私たちのお客様からお話を聞いていても気温の上昇により外出する人が減り、売上に影響を受けています。
気温と売上の相関を理解し、戦略的に活用することは、現代のビジネスにおいて欠かせない視点となっています。感覚に頼るのではなく、データに基づいた意思決定を行うことで、企業はより的確に顧客ニーズに応えることができるのです。
イワサキ経営グループ 監査部3課 勝山健也
- 1 / 1